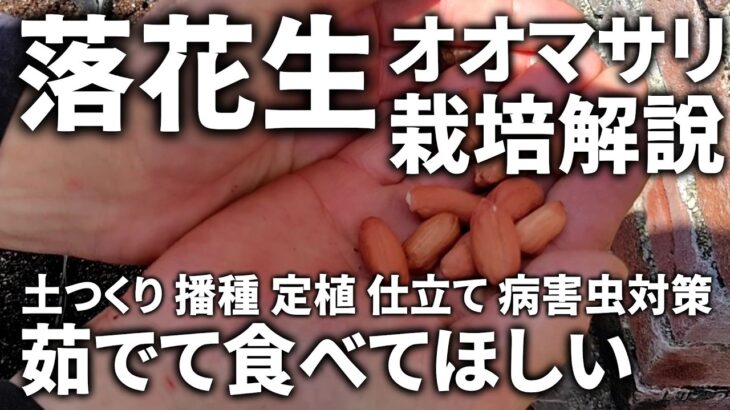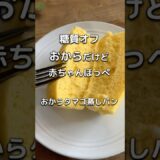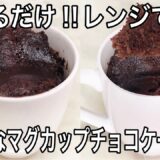オープニング
「落花生は意外と簡単に育てられ、家庭菜園でも人気のある野菜です!」
「今回は種まきから収穫まで、成功のポイントを詳しく解説します!」
「紹介するのは、オオマサリという大粒の実がとれる品種がメインになりますので、まずはほかの品種との違いについて紹介しておきます」
オオマサリの特徴
大粒で収穫量が多い → 一般的な品種の約2倍の大きさで、収穫量は1.3倍以上
甘みが強く、ゆで落花生向き → 柔らかく、甘みがあり、ゆで豆に適している
千葉県で開発された品種 → 「ナカテユタカ」と「Jenkins Jumbo」を掛け合わせて誕生
他の品種との比較
オオマサリは特にゆで落花生向きで、甘みが強く、大粒なのが特徴です。
一方で、ナカテユタカは収穫量が安定し、煎り落花生向き。郷の香は甘みが強く、柔らかい食感が特徴です。
最近登場した「おおまさりネオ」は、オオマサリの改良版で、株がコンパクトになり、収穫量が25%増加する可能性があるとされています。
第1章:種まきの準備
「落花生は直根性なので、移植が苦手。畑に直まきするのがベストです!」
「種をまく前に、水はけの良い土を準備しましょう。」
ラッカセイ(落花生)の種まき時には、いくつかの重要なポイントがあります。適切な管理をすることで、発芽率を高め、健康な苗を育てることができます。
種まきの注意点
適切な時期を選ぶ
気温15℃以上で発芽しやすいため、地域によって種まきの時期が異なります。
一般的には5月~6月が適期ですが、寒冷地では遅霜の影響を避けるため、気温が安定してからまくのがベスト。
土の準備をしっかり行う
水はけの良い砂質土が適しており、pH6.0~6.5の弱酸性が理想。
石灰を適量施すことで、空さや(実が入らない莢)を防ぐことができる。
第2章:種まきの方法
「落花生は深さ3cm程度で、1箇所に2~3粒ずつまきます。」
「種の向きは横に置くと発芽しやすくなります!」
種の向きと深さに注意
深さ3cm程度で、1か所に2~3粒ずつまく。
種の向きは横向きにすると発芽しやすくなる。僕は、芯の部分を下にして植え付けます
水やりの管理
水のやり過ぎはNG! 落花生は乾燥気味の環境を好むため、過湿になると種が腐りやすい。
種まき後は土が乾燥しすぎないように適度に管理し、発芽するまで過度な水やりは避ける。
鳥害対策をする
カラスやハトが種を食べることがあるため、本葉が出るまで不織布やネットをかけると安心。
これらのポイントを押さえることで、発芽率を高め、健康な苗を育てることができます!
第3章:発芽後の管理
「発芽したら元気な苗を選び、1か所1本に間引きします。」
「畑が乾燥しすぎないよう、水やりは朝に行うのがポイントです。」
間引きのタイミング
本葉が2~3枚になったら間引きし、1か所1本にすることで栄養を集中させる。
第4章:仕立て方と病害虫対策
「花が咲いたら、土寄せをして根元をふっくらさせることで、落花生が地面に潜りやすくなります!」
「病害虫対策も重要。アブラムシにはニームオイルスプレーが効果的!」
ラッカセイ(落花生)栽培では、いくつかの害虫や病気に注意が必要です。適切な予防と対策を行うことで、健康な株を育てることができます。
注意すべき害虫
コガネムシ類
被害: 幼虫が地中で根や莢を食害し、株が枯れる原因に。
対策: 土壌をよく耕し、幼虫の発生を抑える。成虫は捕殺するか、ネットで防ぐ。
ハスモンヨトウ
被害: 幼虫が葉を食害し、成長を阻害する。
対策: 早期発見が重要。葉裏をチェックし、見つけたら手で除去するか、BT剤(微生物農薬)を使用。
アブラムシ
被害: 新芽や葉裏に群生し、吸汁することで生育不良を引き起こす。ウイルス病を媒介することも。
対策: 近くにマリーゴールドを植えると忌避効果あり。牛乳スプレーや粘着テープで除去。
注意すべき病気
褐斑病(かっぱんびょう)
症状: 葉に黄褐色の斑点ができ、広がると葉が枯れる。
対策: 風通しを良くし、発病した葉は早めに除去。
白絹病(しらきぬびょう)
症状: 茎葉が黄変し、地際部に白い綿状の菌糸が発生。
対策: 発病株は抜き取り、土を太陽熱消毒する。
そうか病
症状: 葉や莢に褐色の病斑ができ、かさぶた状になる。
対策: 雨で広がるため、発病した部分は除去し、焼却処分。
これらの害虫や病気を防ぐためには、適切な土作り、風通しの確保、定期的なチェックが重要です。
第5章:収穫と保存
「収穫のタイミングは、葉が黄色くなり始めた頃が目安!」
「収穫後は水洗いし、しっかり乾燥させて保存しましょう。」
ラッカセイ(落花生)の収穫時期の目安や収穫方法、保存方法について詳しく解説します!
収穫の目安
種まきから約130日前後が収穫のタイミング。
開花から約75~95日後が目安。オオマサリでは85日~90日(千葉農試データ)
葉や茎が黄色くなり、下葉が枯れてきたら収穫時期。
さやの網目模様がはっきりしているものが80%以上になったら収穫適期。
収穫方法
試し掘りをする
収穫予定の5日前に1株掘り、さやの成長具合を確認。
網目がはっきりしていれば収穫OK!
株元の土を掘り起こす
スコップで根元を掘り、持ち上げるように収穫すると、さやが土中に残りにくい。
力いっぱい引き抜くと、さやが土に残ることがあるので注意。
収穫後の処理
すぐに食べる場合は洗って塩茹ですると美味しい。
乾燥させる場合は土を軽く払い、さやを上にして天日干し(1週間~10日)。
保存方法
乾燥後は網袋に入れ、風通しの良い場所で1か月ほど吊るして保存。
さやを振ってカラカラと音がすればOK。
冷蔵保存は1週間、冷凍保存なら2~3か月可能。
適切な収穫と保存を行えば、美味しい落花生を長く楽しめます!
落花生を煎る方法はいくつかありますが、簡単にできる方法を紹介します!
僕は、煎って食べる方法を試したことがありませんので、参考までに
フライパンで煎る方法
乾燥した落花生を準備(殻付きでもOK)
フライパンを弱火で温める
落花生を入れ、絶えずかき混ぜながら10~13分煎る
パチパチと音がしてきたら、さらに1~2分煎る
火を止めて冷ますと、カリッとした食感に!
オーブンで煎る方法
オーブンを150~160℃に予熱
オーブンペーパーを敷き、落花生を重ならないように並べる
約30~40分焼く(途中でかき混ぜるとムラなく焼ける)
粗熱をとって完成!
電子レンジで簡単に煎る方法
クッキングペーパーを敷き、落花生を広げる
600Wで1分加熱 → かき混ぜてさらに1分 → もう一度かき混ぜて1分
粗熱をとるとカリッと仕上がる!
エンディング「落花生は育てる楽しみも多く、収穫すると達成感があります!」
「ぜひ挑戦して、育てた落花生の写真をコメントでシェアしてください!」
「気楽な家庭菜園」では、家庭菜園に興味がある方や始めたばかりの方に向けて、野菜つくりの楽しさとノウハウをお伝えすべく、菜園作業の様子や理論を中心に、動画をあげています。野菜つくり20年以上の僕と一緒に野菜つくりを目いっぱい楽しみましょう。
#農業 #家庭菜園 #初心者 #野菜つくり #気楽な家庭菜園 #手軽な家庭菜園 #身近な家庭菜園 #素敵な家庭菜園 #気ままな家庭菜園 #堀耕作